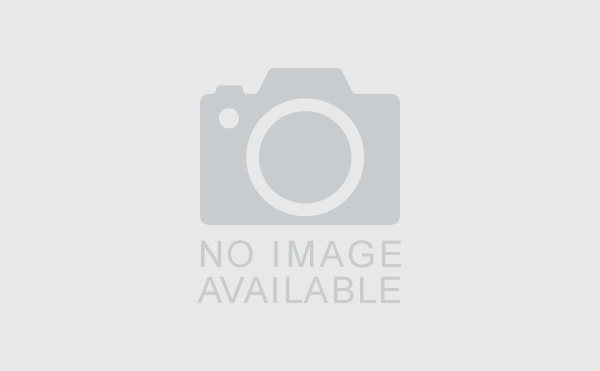2025国際共同組合年フォーラムに参加して ~「共同組合発、子ども・若者が豊かに生きられる社会をつくる」~
国連が2025年を「国際協同組合年」と定めたことを記念して、7月7日(月)横浜にてフォーラムが開催されました。福岡県で長年ホームレス支援や子ども支援の活動を行っているNPO法人抱僕の奥田知志さん基調講演では、家庭の問題を抱えて育った女性の話を伺いました。
教育や家庭状況により社会に適応していけない女性が様々な人のつながりで成長していく姿からご自身も多くのことを学ぶことができたとおっしゃっていました。成長過程の体験は方向次第で良くも悪くもどちらにもなることを知り、子育ての大切をあらためて考えました。基調講演のあとはパネリスト3人による子ども・若者の学校教育の問題・課題や現場からの報告でした。
川崎市で不登校・ひきこもりの子どもや若者の居場所づくりの事業を進めている西田さんは不登校や自死が増えている問題は「学校」の在り方が現在の社会情勢にあっていない、見直すべき時にきている。協同組合から子どもたちが安心して通える「協同組合立の学校」が創れないかと提案がありました。
次に前川さんは、前文部科学省の立場から「そもそも学校は文部省に出先機関、教師は末端の文部官僚である。文部省は指導・助言をおこない拘束力はないので本来ならば住民の自治で学校運営をすることができるが、なぜか従わざるを得ない状況である。」との話で、障害のある子どもが地域社会で学び育つ環境づくりインクルーシブ教育の重要性など興味深い報告でした。
最後はリヒテルズ直子さんのオランダの教育について初めて知ることがたくさんありました。オランダは対立ではなく話し合いで妥協の道を見つけという成熟した市民社会です。学校は社会に向けて子どもを育てる場所、話し合いを通してwinwinな道を探ることを学ばせ自由と責任の意味を教えています。それは「シチズンショプ教育」と呼ばれています。また、子どもたちに社会関与を学ばせるのは地域や保護者の理解と参画が必須とされ、学校が率先して保護者を巻き込んでいくための予算を決める。社会を根本的に変えるのは容易ではないが、「学校」という社会で大人たちが理想の共同体を生み出す努力をすれば社会は変わり始める。この循環は日本の教育にも是非取り入れてほしいと思いました。
様々なお話を聞き、これからは子どもたちの自由と責任を学べる「協同組合の学校」ができればと未来に希望をつなぐフォーラムでした。
最後に川崎市こどもの権利条例 「子どもからのメッゼージ」と「ネルソン・マンデラ」の言葉が心に響きました。ここに記します。
~子どもたちからおとなへのメッセージ~
まず、おとなが幸せにいてください。
おとなが幸せじゃないのに子どもだけ幸せにはなれません。おとなが幸せでないと、子どもに虐待と体罰とかが起きます。
条例に
「子どもは愛情と理解をもって育まれる」とありますが、まず、学校や家庭、地域の中で、おとなが幸せでいてほしいのです。
子どもはそういう中で、安心して生きることができます。
<平成13年(2001年)3月 子どもの権利条例子ども委員会のまとめ>
~ネルソン・マンデラ~ 教育はあなたが世界を変えるために使える、最もパワフルな武器です