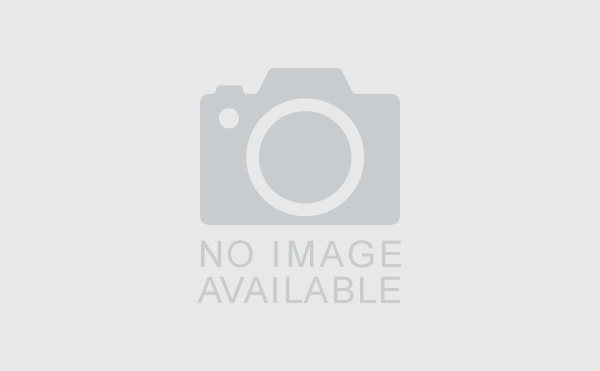「女性と居住の問題について ~居住支援を立ち上げた背景や今の現状を知る~」学習会に参加して
6月21(土)川崎南部ユニット評議員会が開催され、その後の学習会に参加しました。講師は、生活クラブ生協で2023年に居住支援推進企画を立上げた伊藤保子さんです。
生活クラブ生協矢向センターは、配送センターであり、組合員の活動拠点でもある皆さんよくご存知の建物です。センター3Fが昨年改装され「ケア付きシェアハウスNagomo矢向」として居住支援がスタートしました。なぜ居住支援の問題に取り組むことになったのか・・・長いこと保育事業、子育て支援事業に関わってきた伊藤さんは、児童家庭支援センターで子育てに苦労する親のなかに虐待サバイバーが多く、若くして家を離れたいために結婚、妊娠出産するもたちまち育児困難に陥ってしまう、けれど実家には戻れず自立の道も厳しい・・・頼れる身内や信頼できる大人が近くにいないのは決して彼女たちの責任ではない、居住の問題は個人の問題ではなく社会の問題と気付き、居住支援の取り組みを生活クラブに一緒にできないかと提案していったとのことです。居住支援の経緯がよくわかりました。
現実問題として、公的な住宅支援は増えず、賃貸住宅などの手続きも非正規労働者や貧困女性には難しく、世の中は男社会の仕組みで成立されていると実感したそうです。確かに不動産業者が扱う建物・住宅名義などは男性優位に成り立っているのかもしれません。日本の住宅政策は、女・子どもには無いに等しく、家がない人を対象とした制度も今までなく、家族や身近な人に頼れない、実家に戻れない、行き場のない若者・女性は、ますます困難を抱えてしまう。今、本当に必要なのは生活を営むことができる居住支援だということです。居住ができ、安定した生活ができてこそ社会に繋がります。
「Nagomo矢向」はシェアハウスです。住居があることはもちろんですが、食の力も大事なことです。入居者の生活を支える食事を週2回NPO法人メロディーの配食サービスが入り、食を通じて他者、支えている大人たちとの関係が生まれます。建物や部屋があるだけだは「住まい」にはなりません。関わるスタッフと信頼関係があって初めて安心して暮らせる居住⇒「住まい」になっていくのだと思います。矢向センター3Fの居住支援が公助になり、広く公的な制度として発展していけばと願う学習会でした。