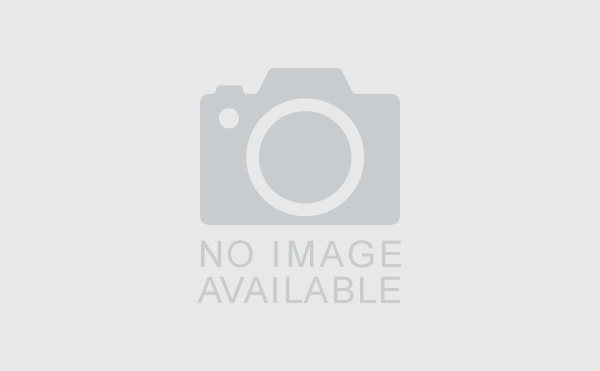部落差別同和問題とは?
6月13日神奈川人権センター主催の「部落差別撤廃の課題」の講座へ参加してきました。
講義を受けて、歴史から見える部落史や今も残る部落差別について知る機会となりました。
初めに、部落解放同盟神奈川県連合会委員であり部落差別当事者から「同対審」答申についての講義を受けました。同対審とは同和対策審議会答申の略語です。1961年に「同和地区に関する社会的および経済的諸問題を解決するための基本的方策」を諮問され、1965年に審議結果が答申されました。答申は全文、同和問題の認識、同和対策の経過、同和対策の具体案、結語(同和行政の方向)から構成されています。
同和問題は人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法に保障された基本的人権にかかわる課題であり、早急に解決することが国の責務で、同時に国民的課題であるとの認識に立って対策をしていかなくては差別がなくならない、と被差別側の立場でもある講師の講話でした。
現実にいまだ部落差別が起きていることは、民主主義の日本であってはならないことです。単なる憶測や思い込みから差別をし、希望の職業につけない、結婚したくとも部落出身だからと反対され破談になる、子どもへのいじめなど実態的、心理的に苦しめられています。日本の歴史の過程において形成された身分階層に基づく差別により、部落出身ということで経済的、社会的、文化的に低位の状態におかれ、だれもが保障されている市民的権利と自由を完全に保証されていないことが重大な社会問題となっています。
行政が積極的に同和問題に取り組み、また私たちもSNSやうその情報に流されず、差別をなくすことを心にとどめなくてはならないと思いました。
続いて、神奈川県の部落史について講義を受けました。そもそも身分制度は江戸時代から見直されました。私のころは士農工商さらに身分の低い「穢多・非人/えた・ひにん」と教科書で学んできましたが、江戸時代は武士、町人、百姓、公家、僧侶・神主、被差別身分と身分制度は上下関係でないようでした。これは現在の教科書に反映されているそうです。
神奈川部落史研究会は神奈川県の部落調査研究を進め、その成果を部落差別問題の解決するための一歩として講座を開いています。今回の講座では確かに差別はあったけれども被差別部落には豊かな教育や文化があったことが資料で示されています。例えば鶴岡八幡宮の祭礼行列では先頭で道を清め役の長吏を務めていたことが古文書から分かり、竹製品、草履や雪駄づくりの技術があったことが明らかです。ではなぜ差別が形成されたのか?「中世から特殊な能力を持った人たち」という見方で穢れに触り、それを除去できる能力、神の通る道を清浄にできる能力、これがかえって人々に怖れとなって次第に遠ざかり差別につながったのではないか? 政治的に作られたのではなく、人々の中に作られ、社会の中で作られたことが部落差別が現代まで根深く続く理由のひとつであり、それは私たちの問題であるということです。
「被差別部落の歴史は社会・地域の歴史と一体となった歴史であり、その歴史の解明は地域の歴史をより豊かにする可能性を持っている。現在に続く部落差別をなくすためには差別の歴史と差別に対する歴史を知ることが大切で無責任な情報に惑わされないようにすること。差別は差別する側の問題であり、私たちの社会全体の問題である。」と述べられていたことに部落差別解消の一歩としたいという熱意を感じました。